社会・地域連携事業について
取り組みについて
同朋大学は地域連携を目的として、2014年3月18日に名古屋市中村区との協定をはじまりに2015年6月4日にあま市、2015年6月5日に津島市と包括連携協定を締結しました。
仏教・文学・歴史・映像・社会福祉・子ども・心理と多岐にわたる同朋大学での教育・研究成果を社会に提供し、地域社会の発展に貢献します。
また、地域と協力したアクティブラーニングの導入やインターン制度の拡充、地域の識者と共同で行う研究などを通じて、地域が求める人材育成を目指します。
仏教・文学・歴史・映像・社会福祉・子ども・心理と多岐にわたる同朋大学での教育・研究成果を社会に提供し、地域社会の発展に貢献します。
また、地域と協力したアクティブラーニングの導入やインターン制度の拡充、地域の識者と共同で行う研究などを通じて、地域が求める人材育成を目指します。
名古屋市中村区との連携
中村区大門地区の活性化を目的とした中村区との新たな連携を構築するため、2014年3月18日同朋大学三大学(同朋大学・名古屋音楽大学・名古屋造形大学)と中村区で協定を 締結しました。
専門的な知識とノウハウを持った大学と、長年地元とのつながりを培って きた区役所が協力することで、三大学が地域の大学として活動し、魅力的なまちづくりにつなげることを目標としています。
「地域振興」「専門知識の活用推進」「地域防災の強化」 の三本の柱をもとに中村区と地域連携事業を展開し、多彩な活動を行っています。
専門的な知識とノウハウを持った大学と、長年地元とのつながりを培って きた区役所が協力することで、三大学が地域の大学として活動し、魅力的なまちづくりにつなげることを目標としています。
「地域振興」「専門知識の活用推進」「地域防災の強化」 の三本の柱をもとに中村区と地域連携事業を展開し、多彩な活動を行っています。
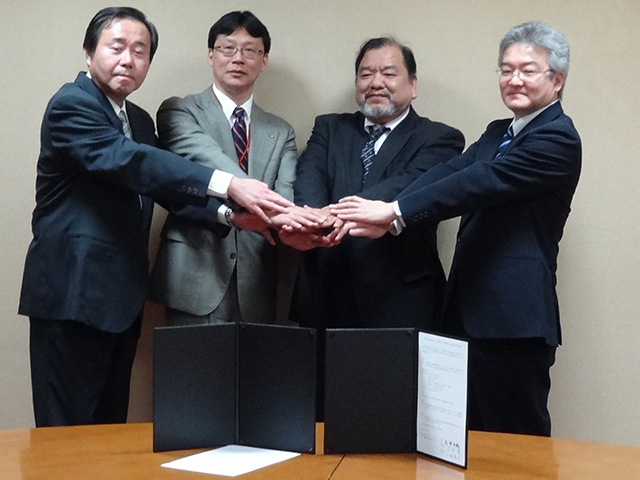
2014年3月18日
中村区 堀場区長らとの連携協定式
あま市・津島市との連携
中村区に続き、2015年6月4日にあま市、2015年6月5日に津島市と連携協定を締結しました。同朋大学はあま市・津島市から一番近い大学になります。あま市・津島市共に大学と連携協定を締結するのは初めてであり、大学が有するノウハウや学生の活力を活かし、地域の問題解決、まちづくり、地域振興、生涯学習、ボランティア、インターンシップ等幅広い分野において協力・連携し活動していきます。その一環として現在あま市交響楽団の舞台撮影が始まっているほか、中村区の有志団体の依頼から始まった「加藤清正」に関するプロモーションビデオ制作についても、清正が幼少のころ過ごした津島市と、清正の盟友「福島正則」と縁のあるあま市を含めて、三つの地域が連携する成果として幅広い活用が見込まれています。
あま市との連携協力事項
あま市及び同朋大学は、次の事項について連携協力する
- まちづくりの推進及び地域の活性化に関すること
- 学校教育、生涯学習、文化及び福祉の向上、スポーツ及び健康づくりの振興に関すること
- 学生ボランティア等の活動及び地域コミュニティの活動に関すること
- 持続可能な社会及び多文化共生社会の構築に関すること
- 地域防災の強化に関すること
- あま市内の企業でのインターンシップの実施に関すること
- 前各号に係る人材育成に関すること
- あま市内の企業への就職紹介に関すること

2015年6月4日 あま市 村上市長らとの連携協定式
津島市との連携協力事項
津島市及び同朋大学は、次の事項について連携協力する
- 地域のまちづくりの推進・活性化
- 歴史文化を活かした地域振興
- 学校教育、生涯学習、文化、スポーツの振興
- 福祉、健康づくり、地域医療の増進
- 学生ボランティア等の活動及び地域コミュニティとの活動
- 持続可能な社会、多文化共生社会の構築
- 地域防災の強化
- 津島市の行政、福祉施設、企業でのインターンシップの実施
- 津島市の企業への就職紹介
- 前1号から9号までのための人材育成
- その他必要と認める事項

2015年6月5日 津島市 日比市長らとの連携協定式
包括連携協定一覧
同朋大学は、地域貢献について地方自治体および地元産業界等と包括的な連携協定を締結しています。
【包括連携協定一覧】(順不同)
社会福祉法人名古屋文化福祉会
社会福祉法人明了会
※ 法人等名称をクリックすると協定先のHPが表示されます。
※ 締結日をクリックすると協定書が表示されます。
※ 締結日をクリックすると協定書が表示されます。
多彩な連携事業
なごや健康カレッジ
―名古屋市健康福祉局研究委託事業―
名古屋市健康増進課から研究委託を受け、大学を活用した地域健康づくりの強化を基本方針に、
- 大学の特徴を活かした健康づくりプログラムによって、市民が健康づくりに取り組む「きっかけ」の提供
- 大学、保健所等を活用し健康づくりの継続を支援する
スクールシネマ・ワークショップ
―独立行政法人国立青少年教育振興機構助成金事業―
東海三県の地域の小中高生を対象とし、2日間で短編映画の企画・撮影・上映会まで行う世代間交流・体験型のワークショップを実施しています。講師は本学教員と、地域で活躍をしている映像業界の方々を迎え、映像文化専攻の学生もボランティアとして参加し、地域の業界・学生・受講者との世代間交流を図るとともに、次世代を担う映像人の育成をめざしています。
キッズカレッジ
―文部科学省 産業界のニーズに対応した教育改善・充実体制整備―
本事業では、今までの個々の教育改善を入学前プログラムと初年次教育の連結のための教材を作成・利用する有機的結合、講義科目での学生参加型授業の拡大、演習科目での共同学習の拡大と問題解決能力の育成、および講義・演習・実習科目との有機的結合を行うことにより、教育改革に全教員がチャレンジしてチームで働いて実施をします。
学部間交流協定
バンドン(インドネシア)のバジャジャラン大学人文学部と同朋大学文学部との学部間交流協定締結
2013年11月1日、バンドン(インドネシア)郊外にあるPadjadjaran大学の人文学部と同朋大学文学部との学部間協定が締結されました。Padjadjaran大学は学生数21,000人、教員数4,900人のマンモス大学で、学士課程11学部、修士課程11研究科、博士課程9研究科を擁するインドネシアで3本の指に入る国立総合大学です。インドネシア語はマレー語であって、ASEANの共通言語にも採択されました。今後ASEANと関係性を深めていくことになる日本の経済界、政界にとっても、インドネシア語の習得は重要であり、私たちの世界もいまや内向きになっていてはやっていけません。これからの人口減少社会の到来に対応して、ASEANとの関係強化は猶予できない状況にあります。教育分野でも、必要な場所に必要な働きかけを、遅延なく行っていかなくてはなりません。今後、交流に向けて協議を深めていきたいと思います。
